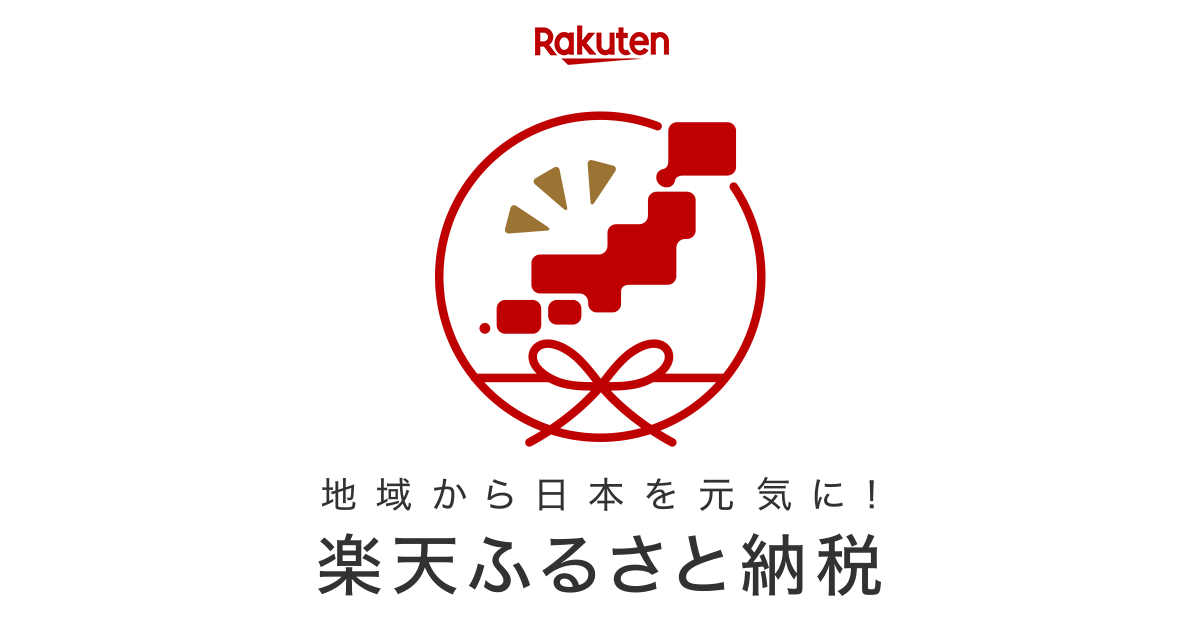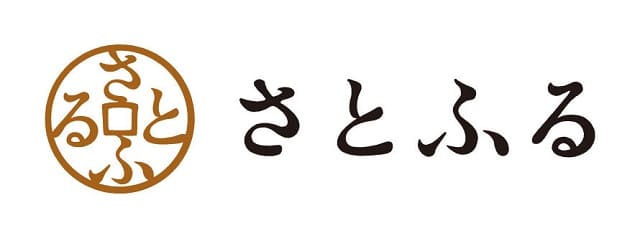ふるさと納税で損する年収は?得するためのチェックポイントを徹底解説
2024/12/19 更新

いまや多くの人々が活用するふるさと納税。返礼品をもらいながら税控除ができる魅力的な制度ですが、仕組みを理解していないとかえって損する可能性もあるんです。
本記事では、ふるさと納税をお得に活用する方法をご紹介します。「損する年収はいくら?」「デメリットは?」といった疑問にお答えしていますので、ふるさと納税で絶対に損したくない方は必見です。
・当サービスに掲載された情報は、編集部のリサーチ情報を掲載しております。記載の内容について(タイトル、商品概要、価格、スペック等)不備がある場合がございます。詳細については、各EC/サービスサイトでご確認の上ご購入くださいますようお願い申し上げます。 なお、当ウェブページの情報を利用することによって発生したいかなる障害や損害についても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご理解いただけますようお願い申し上げます。
・商品PRを目的とした記事です。gooふるさと納税は、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。 当サービスの記事を経由してふるさと納税をすると、売上の一部がgooふるさと納税に還元されます。
目次
また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
この記事でわかること
・ふるさと納税で損する人・得する人
・ふるさと納税の仕組みと注意
・ふるさと納税のメリット・デメリット
ますは控除上限金額を確認!2,000円以上なら損はなし!
\<1分で完了>今年の年収と家族構成を入力するだけ/
ふるさと納税で損する人・得する人とは?
結論、ふるさと納税で得をする人・損をする人は以下のようにわけられます。
ふるさと納税で損する人
①年収150万以下の人
②年収250万円以下で配偶者に収入がない人
③扶養に入っている人
④所得税・住民税を納めていない人
ふるさと納税で得をする人
①年収200万円以上の人
②ある程度「課税所得」のある個人事業主
ふるさと納税が損とも得とも言えない人
①年収150〜200万の人
自分が損をするか得するか確認しよう!
\<1分で完了>今年の年収と家族構成を入力するだけ/
ここからはもう少し詳細に、「ふるさと納税で損する人」「ふるさと納税で得する人」について、ふるさと納税の仕組みに基づいて解説します。
年収250万円以下の人はふるさと納税をする際に注意
ふるさと納税は損をするので行わない方がいい方は、以下のいずれかに該当する方です。
(再掲)ふるさと納税で損する人
①年収150万以下の人
②年収250万円以下で配偶者に収入がない人
③扶養に入っている人
④所得税・住民税を納めていない人
ここからはそれぞれ理由と損をする仕組みを解説します。
①収入150万以下の人
年収150万円以下の方は、返礼品の価値よりもふるさと納税をするための自己負担金2,000円の方が高額になるため、結局損をします。
ふるさと納税は自己負担2,000円で返礼品がもらえるため、「節税」と誤解されますが、正しくは「前納」です。自己負担金の2,000円よりも返礼品の価値が安ければ、ただ多めに納税しただけとなります。
年収150万円以下だと損をする計算とは
上記「限度額シミュレーション」にて「年収150万円」で計算を行った場合、寄附上限額は「9,388円」でした。
このうち、自己負担金が2,000円のため、実際に翌年控除されるのは7,388円です。
さてそれに対して、9,388円の寄附でもらえる返礼品の最大価値は、還元率最大30%であるため、「約2,800円」です。
要するに、年収150万では、最大還元率2,800円ー自己負担金2,000円で、800円しか得になりません。
もちろんそれ以下の年収ではさらに少なくなります。
②年収250万円以下で配偶者に収入がない人
自分の年収250万円以下で配偶者に収入がない人も、ふるさと納税をするメリットはあまりありません。
配偶者に収入がない場合、「配偶者控除」で所得税からの控除が受けられるため、実質的な課税所得が目減りします。
そのため、年収によっては2,000円の自己負担金の方が高くつく場合があります。
③扶養に入っている人
ご家族の扶養に入っている方も、ふるさと納税はするだけ損をします。
100万未満の場合…
住民税・所得税ともに発生しない
103万未満の場合…
住民税は発生するが所得税が発生しない
130万未満の場合…
社会保険料が発生しない
※2023年現在の内容
いずれの状態でも、もともと税金が発生しないのでは、ふるさと納税はするだけ損をします。
④所得税・住民税を納めていない人
「扶養に入っている人」と重複する部分もありますが、以下のような方もふるさと納税は損をします。
・所得がない学生、主婦、主夫
・扶養家族の対象額内で働いているアルバイト
・赤字で申告をする個人事業主
・住民税非課税世帯
③の解説と同じとなりますが、所得税・住民税が発生しなければ、控除するものがなくふるさと納税はするだけ損です。
収入が高ければ高いほどお得にふるさと納税が使える!
(再掲)ふるさと納税で得をする人
①年収200万円以上の人
②ある程度「課税所得」のある個人事業主
①年収200万円以上の人
年収200万円以上の会社勤めの方は、ふるさと納税を利用した方がお得です。自己負担2,000円以上の価値のある返礼品がもらえます。
ふるさと納税は所得金額に比例して寄附上限額も高くなるため、収入が高ければ高いほど返礼品の価値も上がりよりお得になります。
ちなみに、会社員の方は「ワンストップ特例制度」を使用すれば、確定申告は不要です。
年末調整時の書類も特に不要であるため、会社員の方でも手続き的な不利はなくふるさと納税できます。
②ある程度「課税所得」のある個人事業主
ある程度所得が見込まれる個人事業主の方も、ふるさと納税はした方がお得になります。
ただし個人事業主の方の課税所得は、小規模共済の掛け金等で大きく変わってくるため、一概にいくら以上とは言えません。
詳しくは詳細シミュレーターでご確認ください。
初心者向け!
\漫画や動画でわかりやすく解説/
「どんな返礼品がもらえる?」
\すぐに返礼品を選びたい方はこちら/
補足|年収200万円以上でも、配偶者控除などその他控除で寄附上限は目減りする
ふるさと納税は他に受ける控除があり課税所得が減る場合は、寄附上限も減ります。そのため、年収200万円以上でも金額によっては損をします。
たとえば、
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 寡婦控除
- 小規模共済控除
- 生面保険料控除
などが該当します。
年収300万円を超えたら、ふるさと納税以外の控除があっても、ほとんどの方はお得になります。
しかし年収250万円未満で、ふるさと納税以外に控除のある方は、シミュレーターで計算してみるのをおすすめします。
「返礼品の価値」ー「2,000円」がお得になる金額!
(再掲)ふるさと納税が損とも得とも言えない人
①年収150〜200万の人
会社員で年収が150〜200万円の場合、ふるさと納税をしても大幅なメリットは見込めません。しかし、確実に損をするとも言えません。
これら年収の方がふるさと納税をした場合、寄附上限額と返礼品の最大価値は以下のようになります。
年収200万円以下の場合の寄附金額上限目安
| 年収 | 寄附額上限目安 |
| 150万 | 9,388円 |
| 170万 | 12,729円 |
| 190万 | 15,152円 |
※楽天ふるさと納税の簡易シミュレーターにて
※既婚・扶養家族なし・配偶者控除なし設定
上限まで寄附した場合の返礼品の最大価値
| 年収 | 返礼品の最大価値 |
| 150万 | 約2,700円 |
| 170万 | 約3,800円 |
| 190万 | 約4,500円 |
※金額はあくまで目安です
※還元率最大30%
「返礼品の価値」-「2,000円」がお得になる金額
要するに、返礼品の価値が自己負担金以下〜同等か多少お得になる程度のため、大きなメリットは得られません。
返礼品は寄附金額の最大30%の還元率のため、低いものを選んでしまうと損をします。
そもそもふるさと納税とは?
最近ふるさと納税というワードをよく耳にする方も多いはずです。ここではふるさと納税とは何なのか、どんな仕組みなのかを簡単にご紹介します。
応援したい自治体に「寄附」できる制度
ふるさと納税とは、翌年の市民税を前納する形で、任意の自治体に寄附しその見返りとして返礼品をもらう制度です。
過疎化が進んでいる地方の税収や、地域産業の発展を目指すべく始まった制度です。総務省の「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、令和4年度の「控除適用者数(=ふるさと納税者数)」は全国741万人におよび、令和元年と比べてほぼ倍増しています。
寄附金額によって貰える豪華な返礼品も人気の理由で、地域に根付いた美味しい特産品だけでなく、地方に工場を構える企業の生活雑貨も手に入ります。
地方自治体に寄附した金額で「税金の控除」を受けられる
ふるさと納税額から2,000円を差し引いた金額は、所得税としての還付、あるいは翌年の住民税から控除されます。
- 確定申告の場合は「所得税の還付+翌年の住民税の控除」
- ワンストップ特例を活用すると全額「翌年の住民税の控除」
このようになります。
自己負担金の2,000円以外は全額そのまま差し引かれて返礼品がもらえるため、大変お得感のある制度です。
ただし、「控除上限=ふるさと納税の寄附金の上限」は収入やその他控除状況によって異なるため、ふるさと納税をする前には寄附しすぎないように必ず計算・シミュレートをするのが望ましいです。
ふるさと納税で損をしないための注意点をチェック!
ふるさと納税で損をしないために、理解しておくべき仕組みがあります。
ふるさと納税で理解すべき仕組み
①控除されるのは本人名義の寄附のみ
②その他の控除が多いと寄附上限が減る
③ワンストップ特例制度はマイナンバー必須
④確定申告が必要になる場合がある
①控除されるのは本人名義の寄附のみ
ふるさと納税を行なって控除されるのは、本人名義の寄附のみです。家族が行っても控除されません。
特にクレジットカード経由で寄附する場合は、「本人名義のクレジットカード+本人名義の寄附」が一致しているかが重要です。
もしも家族のクレジットカードで寄附した場合、無効とされる可能性があります。
②その他の控除が多いと寄附上限が減る
すでに解説した内容とやや重複しますが、ふるさと納税以外の控除が多い場合は、寄附上限が減ります。
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 寡婦控除
- 生面保険料控除
- 住宅ローン控除
などが該当しないかご確認ください。
③ワンストップ特例制度はマイナンバー必須
ワンストップ特例は確定申告不要で会社員の方にとって恩恵の大きな制度です。しかし、申請にはマイナンバーが必要になります。
申請できるパターンは以下です。
| パターンA |
|
|
| パターンB |
|
or マイナンバーの記載されている住民票の写し
+
運転免許証のコピー or パスポートのコピー |
| パターンB |
|
or ・マイナンバーの記載されている住民票の写し
+
|
また、ワンストップ特例制度をオンラインで申請する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。iPhoneといったICカードリーダーとして使用できるスマートフォンでも可です。
④確定申告が必要になる場合がある
ワンストップ特例制度で確定申告をしなくていい…と思っていても、実は確定申告が必要な場合があります。以下のようなパターンです。
- 6自治体以上にふるさと納税をした
- ワンストップ特例期日の1月10日に間に合わなかった
- 医療費控除を申請する
- 住宅ローン申請の初年度の申請をする
もちろんこれ以外に、もともと確定申告が必要な個人事業主の方や副業をしている方なども含まれます。
ふるさと納税をする大きな3つのメリット
ふるさと納税は「お得に地方の特産品を受け取れる」イメージを持つ方が多いです。しかし、ふるさと納税のメリットはそれだけではありません。主な3つのメリットをご紹介します。
メリット①簡単な手続きだけで「税金の控除」を受けられる
ふるさと納税の1番のメリットは、返礼品がもらえるのに税金の控除ができる点です。
所得税からの還付、あるいは翌年市民税の控除の形で、自己負担金2,000円を除いた寄附金が全額控除されます。
また会社員の方は確定申告なしで「ワンストップ特例制度」により、郵送またはオンラインで申請が簡単なのもメリットです。
マイナンバーカードとiPhoneなどのICカードリーダーになるスマートフォンがあれば、郵送の手間すらかかりません。
好きな地域の「豪華特産品」をもらえる
ふるさと納税は、選んだ自治体にちなんだ特産品が返礼品としてもらえます。
肉魚介といった生鮮食品やハムソーセージなど加工品はもちろん、その地域の伝統工芸品や、本社を置くメーカーの電化製品や雑貨など、種類は多岐にわたります。また観光地ならその地への招待といった体験型の返礼品もあります。
返礼品の還元率は寄附額に対して最大30%と取り決めがあるため、寄附額が高い人ほど返礼品の内容も充実します。
「特産品をもらう以外の使い道」も選べる
ふるさと納税といえば「返礼品が豪華」なイメージが先行していますが、被災地を支援する災害支援や医療機関充実のための資金などへの寄附も可能です。
特に、こどものための学校支援金や社会環境の整備は人気を集めています。将来家族で住みたい場所や生まれ育った地元への寄附で、ご自身の税金の使い道を明確にできるのも嬉しい点です。
地元の発展に向けて寄附したあとは「自治体からの使い道情報」でふるさと納税の活用状況を把握できますので、ふるさと納税で社会貢献に寄附した方はぜひチェックしてみてください。
ポイント還元や魅力的なキャンペーンもある
各ふるさと納税サイトではPayPay・au Pay・Amazon Payなどの付与のほか、独自のポイント制度を設けています。また、よりお得にポイントが貯まりやすかったり、ギフトカードがもらえたりなどのキャンペーンを開催しているサイトもあります。
そのほか、会員登録・寄附の申し込みなどで賞品がもらえるキャンペーンを開催しているふるさと納税サイトもあるので、ふるさと納税を利用している方やこれからふるさと納税を始める方は要チェックです。
ふるさと納税におけるキャンペーンコードについて詳しくはこちら!
ふるさと納税のデメリットを理解して最大限お得に寄附をしよう
簡単に税金控除ができると言われるふるさと納税ですが、知らずに利用すると失敗しかねないデメリットもあります。ここでは主なデメリットを5つご紹介しますので、利用前に必ず確認しましょう。
住民票のある自治体に寄附すると「返礼品を受け取れない」
ご自身が住んでいる地域にふるさと納税で寄附を行うと、税額の控除を受けられても返礼品がもらえません。
ふるさと納税とは、本来自分の地域に支払う税金を他自治体に寄附の形で納め、代わりに控除を受けるものです。返礼品はあくまで寄附してもらった地方自治体からのお礼であるため、ご自身の住んでいる地域で行なえば本来の税金支払いと同様になります。
ご自身が住む地域でふるさと納税を行う場合も、地方自治体への寄附と同じような手続き・時間・お金がかかります。ふるさと納税を考えている方は、ご自身の住んでいるところ以外の地域に寄附しましょう。
年間6自治体以上に寄附した場合は「確定申告」の必要がある
会社員の方で確定申告なしでふるさと納税をするには、5自治体以下におさえなければなりません。6自治体以上に寄附をすると確定申告が必要です。
また、ふるさと納税は同一の自治体に何度も返礼品を申し込みも可能です。
同一自治体への寄附は、何度寄附しても1自治体としてカウントされます。
寄附した自治体が5つ以内なら「ワンストップ特例制度」が使える!
年間5つ以内の自治体でふるさと納税を利用した方は、確定申告を行わなずに税額控除ができる「ワンストップ特例制度」が利用できます。年末の面倒な計算や書類記入をしなくて済むため、もともと確定申告を行う必要がない方は積極的に活用するべきです。
ただし、年間6自治体以上に寄附した場合・フリーランスやアルバイトで確定申告を行う義務がある方は利用できませんので、ふるさと納税利用前に利用の可否を確認しましょう。
ちなみに、確定申告とワンストップ特例制度を併用すると、ワンストップ特例制度が無効化され確定申告が優先されます。
寄附上限額を超えると損をする
ふるさと納税を利用して控除できる税金額には上限があります。上限額を超えると、ただ余分に納税しただけとなるため、あらかじめ限度額の確認が必要です。
控除できる上限額は所得税・住民税でそれぞれ異なります。所得税は総所得金額の約40%、住民税は総所得金額の約30%です。住民税は基本分だけでなく「特例分」の控除もありますので、計算時に確認しましょう。
本記事では、控除上限額の目安一覧表の他に、ご自身でできる計算方法も記載しています。合わせてご覧ください。
※詳しい計算方法や税率は自治体によって異なります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
寄附金額に関わらず「2,000円は自己負担」しなければならない
返礼品の数に限らず、ふるさと納税を利用する方全員が2,000円の自己負担を伴います。
地方自治体への寄附額から自己負担2,000円を引いた額が税金の控除を受けられる金額になりますので、計算時に確認しましょう。
また、控除上限額を上回った寄附をした場合、実質「多めに納税しただけ」となります。
控除上限額を越えない限りは年間2つ以上の自治体に寄附しても自己負担額2,000円のみですので、ご自身の収入を元に控除上限額を把握しておくとプラスの出費を防げます。
控除されるのは「翌年の6月以降の住民税」になる
ふるさと納税を利用し住民税が控除されるのは、翌年6月以降です。毎月6月に住民税が決定し、この金額がすでに控除されたものとなります。
控除上限額は収入を元に計算されるため個人差はありますが、多額の寄附で控除を受ける方もいるはずです。手元金が少ないときにふるさと納税を利用すると負担になってしまいますので、余裕があるときの利用をおすすめします。
名義の異なる場合は所得税・住民税が控除されない
ふるさと納税において所得税・住民税の控除は、寄附者の名義分しか認められません。
たとえば、扶養内の妻が夫名義のクレジットカードで寄附の申し込みを行っても、妻は控除に必要な「寄附金受領証明書」が有効にならないため注意が必要です。
給与・家族構成別「控除限度額目安の早見表」
| ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
| 独身 又は 共働き※1 |
夫婦※2 又は 共働き + 子1人(高校生※3) |
共働き + 子1人(大学生※3) |
夫婦 + 子1人(高校生) |
共働き + 子2人(大学生と高校生) |
夫婦 + 子2人(大学生と高校生) |
|
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
| 325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
| 375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
| 450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
| 475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が141万円以上の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている場合)
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4「中学生以下の子供」は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
出典:総務省|ふるさと納税ポータルサイト
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)
(”全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安”より一部抜粋)
控除上限額を「あらかじめ計算」しておこう
ふるさと納税で利用できる控除上限額目安一覧表をご紹介しました。あくまで目安ですので、実際の金額とは異なる場合があります。
一般的な控除額の計算方法は以下のとおりです。
A.所得税控除額=(ふるさと納税額ー2,000円)×所得税の税率
住民税の控除には基本分・特例分の2種類があります。
B.基本分の住民税控除額=(ふるさと納税額ー2,000円)×10%
C.特例分の住民税控除額=(寄附額ー2,000円)
×(100%ー10%(基本分)ー所得税の税率)
※特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合
D.特例分の住民税控除額=(住民税所得割額)×20%
※特例分(Cで計算した場合の特例分)が住民税所得割額の2割を超える場合
参考:総務省|ふるさと納税ポータルサイト
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html)(”控除額の計算”より)
さらに具体的な数値を知りたい場合は、ふるさと納税関連の各サイトで控除上限額シミュレーターがありますので、源泉徴収票を用意して利用してみましょう。
ふるさと納税で得する人・損する人に関するよくある質問
ここではふるさと納税における得する人・損する人に関するよくある質問を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ふるさと納税で医療費控除を受ける場合は損をする?
医療費控除を受ける場合、控除上限額の範囲内でふるさと納税を行えば損はしません。この場合も、2,000円の寄附額を超える範囲が所得税と住民税から控除されるため、どれだけ高額の寄附を行っても、実質2,000円の負担で返礼品がもらえます。
ふるさと納税における医療費控除の併用についてはこちら!
産休・育休中のふるさと納税は損をする?
産休に入ったその年の年収、あるいは育休が明けた年の年収が200万円以上になりそうなら、ふるさと納税はしたほうが得になります。
ただし、1年以上産休や育休を取得しており収入がない方は、もともと課税所得・翌年の住民税が発生しないため、ふるさと納税をしても控除は受けられません。
厳密にはふるさと納税はできても、全額自己負担で寄附をしただけとなります。
ふるさと納税における産休・育休中についてはこちら!
どこのふるさと納税サイトがお得に利用できる?
ふるさと納税を利用する際、ふるさと納税サイトごとでお得に利用できる点が異なります。各ふるさと納税サイトで導入しているポイントシステムやキャンペーンなどにより、ポイント還元率やお得なキャンペーンがさまざまです。
ふるさと納税のおすすめサイトの紹介はこちら!
まとめ
本記事のまとめは以下のとおりです。
ふるさと納税で損をするのは…
①年収150万以下の人
②年収250万円以下で配偶者に収入がない人
③扶養に入っている人
④所得税・住民税を納めていない人
ふるさと納税で得をするのは…
①年収200万円以上の人
②ある程度「課税所得」のある個人事業主
ふるさと納税のメリット・デメリットを理解して、気になる返礼品を選びましょう。今年のふるさと納税は12月31日までです!
ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2024年12月19日)やレビューをもとに作成しております。