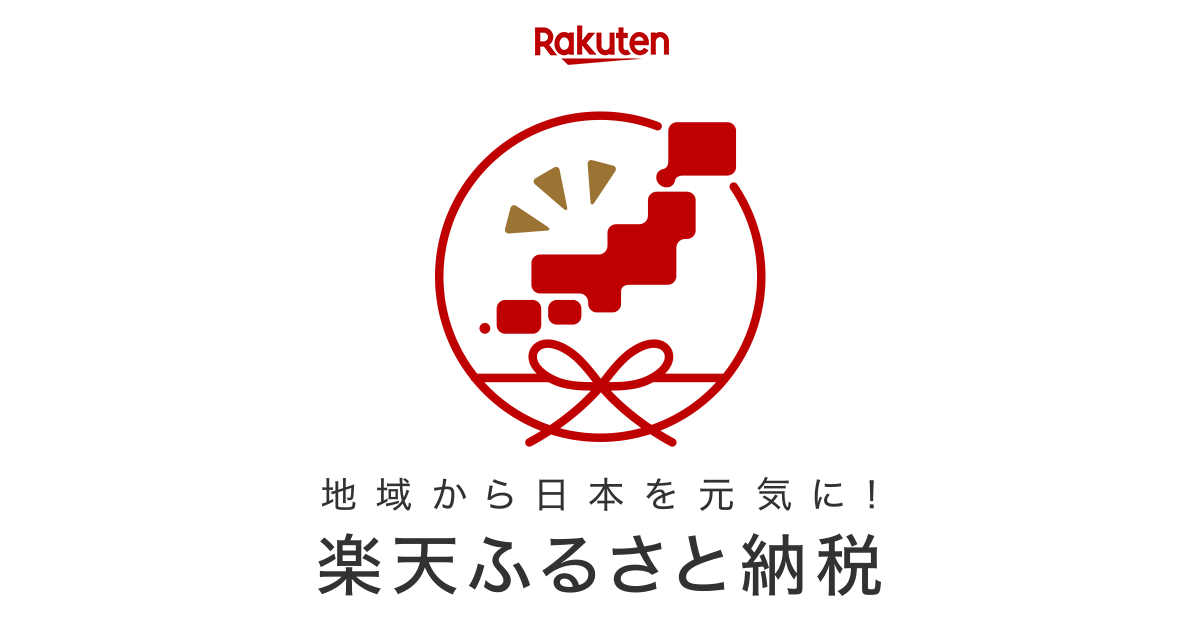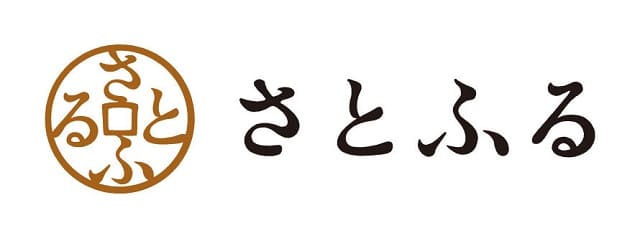ふるさと納税の限度額は源泉徴収票で確認できる!ない場合の対処方やどこを見るのかを解説
2024/11/18 更新

出典: pixabay.com
ふるさと納税の控除限度額はその年の年収で決まるので、会社員・公務員などの方は源泉徴収票で確認することになります。また源泉徴収票はふるさと納税の申請時に行う、確定申告の際に必要になる可能性があります。
今回はふるさと納税をした際に知りたい源泉徴収票の見方や、失くしてしまった場合の対処法などを解説していきます。
・当サービスに掲載された情報は、編集部のリサーチ情報を掲載しております。記載の内容について(タイトル、商品概要、価格、スペック等)不備がある場合がございます。詳細については、各EC/サービスサイトでご確認の上ご購入くださいますようお願い申し上げます。 なお、当ウェブページの情報を利用することによって発生したいかなる障害や損害についても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご理解いただけますようお願い申し上げます。
・商品PRを目的とした記事です。gooふるさと納税は、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。 当サービスの記事を経由してふるさと納税をすると、売上の一部がgooふるさと納税に還元されます。
目次
また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
推定年収は今年の源泉徴収票の「支払い金額」欄を確認
ふるさと納税をするとき「源泉徴収票」はどこを見る?
・「支払金額」欄がボーナスを含めた金額であり、シミュレーターの年収に該当
・2024年1月1日〜12月31日に支払が確定した給与・賞与
・転職や独立した場合は、退職した会社の「給与所得の源泉徴収票」と現在の収入で推定
\30秒で上限金額を計算できる!/
「支払い金額」と「家族構成」を入力するだけ!
\詳細なシミュレーションを行う際の源泉徴収票の見方はこちら/
※記事内の該当箇所に移動します
\調べた限度額をもとに返礼品を選びたい方はこちら/
限度額の確認方法
限度額はシュミレーションサイトで以下を入力するだけで、簡単に算出できます。
- その年の年収
- 配偶者/扶養家族の有無
簡易的ではあるものの、税理士監修のシュミレーション制度なので目安には十分です。
\30秒で上限金額を計算できる!/
「支払い金額」と「家族構成」を入力するだけ!
源泉徴収票がない場合は給与明細や住民税決定通知書から年収を推定
源泉徴収票が手元にない場合の限度額の確認方法は、給与明細や住民決定通知書を使った年収の推定です。源泉徴収票を紛失した、提出や再発行していて年内に間に合わない場合の対処法も解説するので、参考にしてください。
紛失した・提出して手元にない場合
源泉徴収票を紛失した場合は、勤務先の担当部署に再発行を依頼しましょう。源泉徴収票の再発行は義務なので、ほとんどの場合は応じてくれます。拒否された際は税務署に相談してください。
源泉徴収票を提出して手元にない場合も、上記と同様の対処で問題ありません。源泉徴収票は確定申告にも必要なので、再発行して備えておきましょう。
発行が年内に間に合わない場合
源泉徴収票の発行が年内に間に合わない場合は、給与明細や住民税決定通知書を基に限度額のシミュレーションを行なってください。給与明細に記載の税引前の金額12か月分+ボーナス分を足すとおおよその年収を算出できます。
住民税決定通知書を使う場合は、住民税をもとに市町村の所得割額と都道府県の所得割額を使って算出できます。給料から引かれている住民税は「年間の住民税÷12」の金額なので、市町村民税所得割に住民税×12の金額を入力してください。
ただし、この計算での金額は「課税所得」のため、正確な数値ではありません。
源泉徴収票は確定申告時にも必要
源泉徴収票は控除上限額のシミュレーションだけでなく、確定申告の際にも必要です。ワンストップ特例制度を利用した方以外は、確定申告時にふるさと納税の控除申請を行ないます。
また、ワンストップ特例制度を利用しても、ふるさと納税の控除申請が必要な場合があります。以下の条件に1つでも当てはまる方は対象です。
- 1年を通して6自治体以上に寄附した
- 複数寄附したうちのどれか1つワンストップ特例の申請書を提出できなかった
- 給与所得者かつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要
▼確定申告の手順がわかりやすく解説されています
▼「ワンストップ」と「確定申告」で申請する際の違いを詳しく解説
\30秒で上限金額を計算できる!/
「支払い金額」と「家族構成」を入力するだけ!
控除上限額のシミュレーション
ふるさと納税の各サイトは控除上限額のシミュレーションを設けているところが多く、ご自身の年収などの情報を入力すれば、その年に寄附できる目安の上限額が分かります。この「年収」を入力する際に、前年の源泉徴収票が参考になります。
源泉徴収票は一般的には年の初めに前年分のものが渡される場合が多いですが、その時点ではもう前年内のふるさと納税は締め切られているため、控除上限額の参考にできません。
そのためシミュレーションにあたっては「前年の源泉徴収票」を参考にするケースが多くなると考えられます。
▼源泉徴収票の「支払金額」を「年収」に入力して計算する!
源泉徴収票の各項目の見方をチェック
源泉徴収票には数字や項目がたくさん記載されていて、見方がわかりにくいです。しかし、給与や納税額の把握は大切です。特に確定申告が必要な方や収入証明に源泉徴収票を使用する方は、各項目の意味や内容をしっかりチェックしましょう。
支払い金額
支払金額はその年の1月~12月中に支払われた給与の総額で、上限額の計算や確定申告時に必要です。手取り金額ではなく、税金や保険料が引かれる前の額面支給の金額が記載されています。
給与所得控除後の金額
支払金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。個人事業主の場合は必要経費、給与所得者は国税庁の定めによる一定額を経費として年収から差し引きます。
| 給与などの収入金額 | 給与所得控除 |
| 180万円以下 |
収入金額×40%-10万円 55万円未満は55万円 |
| 180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
(例)給与などの額面が350万円の場合
350万円×30%+8万円=113万円
350万円から113万円を差し引いた237万円が給与所得の金額です。
所得控除の額の合計額
所得控除後の額の合計額は、給与所得控除以外の控除の合計額です。毎月給料から天引きされてきた健康保険料や厚生年金保険料などの合計と、年末調整によりはじめて控除される、配偶者控除や基礎控除などがあります。以下の一覧表でご覧ください。
| 控除の種類 | 控除が受けられる場合 |
| 社会保険控除 | 健康保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年金保険料・国民年金基金の掛け金・厚生年金保険料など支払った場合に適用される控除。同一生計の配偶者その他の家族も含まれる。 |
| 小規模企業共済金等掛金控除 | 小規模企業共済掛金を支払った場合に適用される控除 |
| 生命保険料控除 | 生命保険・介護保険料・個人年金を支払った場合に適用される控除 |
| 地震保険料控除 | 地震保険を支払った場合に適用される控除 |
| 障害者控除 | 納税者や同一生計配偶者、扶養家族が障害者の場合適用される控除 |
| 寡婦(寡夫)控除 | 納税者の所得が550万円以下で、配偶者と死別または離婚して扶養家族がいる場合に適用される控除 |
| ひとり親控除 | 納税者の所得が550万円以下で、納税者がひとり親である場合適用される控除 |
| 勤労学生控除 | 学校に行きながら働いている場合に適用される控除 ※ただし合計所得額75万円以下 |
| 配偶者控除 | 納税者の所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が48万円以下の場合適用される控除 |
| 配偶者特別控除 | 納税者の所得が1,000万円以下で、配偶者の所得が合計48万以上133万円以下の場合適用される控除 |
| 扶養控除 | 合計所得が48万円以下である16歳以上の子供や両親を扶養している場合に適用される控除 |
| 基礎控除 | 納税者の合計所得が2,500万円以下である場合に適用される控除 |
上記以外の医療費控除・寄附金控除・雑損控除は年末調整の対象外となっていますので、控除を受けるためには別途確定申告をする必要があります。寄附金控除に関してはふるさと納税の場合、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要です。
\30秒で上限金額を計算できる!/
「支払い金額」と「家族構成」を入力するだけ!
源泉徴収税額
源泉徴収税額は1年間で徴収した所得税の合計額が記載されています。課税対象額は給与所得控除後の金額から、所得控除後の額の合計額を差し引いて算出します。源泉徴収税額はその金額に税率を掛けたものです。以下の一覧表を参考にしてください。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円~329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円~694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円~899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円~1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1,800万円~3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 50% | 479万6,000円 |
源泉徴収票は上記のように、収入に応じた税率で計算されています。源泉所得税は会社で給与などから差し引かれた所得税ですが、すでにご自身で納めた税金と言えます。
毎月所得税が天引きされるため、年末調整や確定申告時の納税額の負担が軽くなるメリットがあります。
(源泉)控除対象配偶者の有無等
控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち本人の合計所得額が1,000万円(給与収入が1,195万円)以下の方です。対象の配偶者がいる場合に「有」に〇がつきます。配偶者の所得が48万円以上である場合は無しになります。
また、「従有」欄は給料を2カ所からもらっている場合に〇がつきます。その場合は他の給与所得の方で配偶者控除を受けています。「老人」に〇がついている場合は、配偶者控除の対象者が70歳以上を表しています。
配偶者(特別)控除の額
配偶者特別控除は、配偶者を養っている納税者の所得合計が1,000万円以下の方が対象です。対象として扱われる配偶者は、年間所得額の合計が103万円以下であり基礎控除額が48万円以下である必要があります。
また、配偶者控除特別控除の金額は、納税者本人の所得合計によって変わってきます。配偶者控除とは異なり、配偶者との合計所得によっても控除される金額が変動してきます。
以下の表を参考にご自身と、配偶者の収入が該当する欄をご確認ください。
| 配偶者の合計所得額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
| 48万円~95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超~100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超~105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超~110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超~115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超~120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超~125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超~130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超~133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
上記表のとおり、配偶者との収入合計により控除される金額が段階的に変動します。例えば、夫の所得合計600万円・妻の所得合計120万円の場合は11万円の控除が受けられます。
納税者本人の所得合計が1,000万円を超える場合は対象外です。
控除対象扶養親族の数(配偶者を除く。)
控除対象扶養親族の数の欄は、配偶者を除いたその他の扶養親族の人数が記載されます。
<親族の区分>
- 特定:その年の12月31日現在で16歳以上23歳未満
- 老人:その年の12月31日現在で70歳以上
- その他:「特定」と「老人」に該当しない16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満
16歳未満扶養親族の数
16歳未満扶養親族の数の欄は、その年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族が何名かを記載しています。16歳未満の方には児童手当が付与されるため、扶養控除の対象外です。
ただし、扶養人数には加算されるので、合計所得によっては市県民税の非課税規定が適用される場合があります。
障害者の数(本人を除く。)
「障害者の数(本人を除く。)」欄は、扶養している親族に障害者がいる場合の人数です。
<区分>
- 特別:特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族
(※同居特別障害者に該当する者の数は内書き記載) - その他:特別障害者以外の障害者人数
社会保険料等の金額
社会保険料等の金額の欄は、1年間で支払った社会保険料の額です。健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・介護保険料の合計が記載されています。年末調整時にご自身やご家族の国民年金など自己負担した社会保険料を申告すれば、その金額も合算されます。
生命保険料の控除額
生命保険料の控除額の欄は、年末調整で提出した申告書から算出された控除額です。源泉徴収票の下の欄にある「新生命保険料の金額」から「旧個人年金保険料の金額」の5項目で計算され、所得税は12万円、住民税は7万円まで控除できます。
地震保険料の控除額
地震保険料の控除額の欄は、その年に支払った地震保険料と「旧長期損害保険料の金額」に応じた所得控除額が記載されます。
平成18年の税制改正で損害保険料控除は廃止されましたが、経過措置として特定の要件を満たす長期損害保険料については地震保険料控除の対象です。
<対象条件>
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以後の場合は対象外 )
- 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、どちらか一方のみの控除が適用されます。上限は5万円です。
住宅借入金等特別控除の額
住宅借入金等特別控除の額の欄は、年末調整にて控除された住宅ローン控除の額です。所得控除とは異なり、最終的に算出された所得税から直接差し引けます。住宅を取得した年は、確定申告による手続きが必要です。
税制改革で控除期間や控除率が変わるので、借入する際は何年控除が受けられてどれくらい控除されるのか確認しましょう。
本人が障害者
本人が障害者欄はご自身が障害者の場合で、特別障害者は「特別」・普通障害者は「その他」に区分されます。特別障害者の方は40万円、普通障害者の方は27万円の控除が受けられます。
ご自身が特別とその他のどちらに当たるのか、以下の表を参考にご覧ください。
| 障害の内容 | 普通障害者 | 特別障害者 | |
| 1 | 精神上の障害により事理を弁護する能力を欠く常況にある方 | - | 該当するすべての方 |
| 2 | 精神保健指定医などから知的障害者と判定された方 | 中度または軽度と判定された方(療育手帳の障害の障害程度がBの方) | 重度と判定された方(療育手帳の障害の程度がAの方) |
| 3 | 精神に障害がある方で精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 | 右の程度以外の方 | 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方 |
| 4 | 身体障害者手帳に身体上の障害がある方として記載されている方 | 障害の程度が3級から6級までの方 | 障害の程度が1級または2級の方 |
| 5 | 戦傷病者手帳の交付を受けている方 | 右の程度以外の方 | 障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの方 |
| 6 | 原子爆弾の被ばくによる障害者として厚生労働大臣の認定を受けている方 | - | 該当するすべての方 |
| 7 | 常に就床を要し、複雑な介護を要する方 | - | 該当するすべての方 |
| 8 | 年齢が65歳以上で、福祉事務所長などから認定されている方 | 右の程度以外の方 | 1・2・4の特別障害者と同程度の障害がある方 |
障害者控除を受ける場合は申請が必要です。勤務先に提出する書類に記載し、控除を受ける意思表示をしないと、控除が受けられません。具体的には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の欄に記載をして申告します。
寡婦・ひとり親
寡婦・ひとり親※の欄は、寡婦(寡夫)控除がある場合〇が入ります。配偶者と死別または離婚をして再婚していない方が受けられる控除です。寡婦・寡夫ともに27万円が控除されます。ただし、以下の条件があります。
- 配偶者と死別または離婚をしており、現在も独身
- 合計所得額が500万円以下
- 年齢を問わず扶養している親族がいる
- 12月31日の時点で判定
※令和2年分から寡夫→ひとり親に変更
なお、上記要件を満たしていても寡婦の方がひとり親控除を受ける場合は、寡婦控除の対象外です。ひとり親控除の創設により、これまで寡婦控除対象だった方も対象外になったり、控除額が変更になったりする場合もあります。
勤労学生
勤労学生欄は学生でありながら企業に勤務し、給与所得がある場合に〇が入ります。学校に通いながら会社に勤める学生の税負担を年末調整で優遇する控除です。勤労学生控除の額は27万円ですが、ある一定の要件を満たしている必要があります。
要件として、勤労による給与所得額が年間65万円以下で、なおかつ配当所得・不動産所得など給与以外の所得が10万円を超えていない方が対象です。さらに以下の3つの項目のうちいずれかに該当している必要があります。
- 学校教育法の第1条で規定された小中高・高専・大学などの学生や生徒・児童
- 職業能力開発促進法の規定によって認定を受けている職業訓練校で要件に該当する課程を学んでいるもの
- 国や学校法人・地方公務団体・農協協同組合連同会・医療法人などが設立した専修学校をはじめとする各種学校に通う生徒で、職業に必要とされる技術を教えるなど、要件に該当する課程を学んでいるもの
年間65万円の給与所得は、給与所得控除で65万円差し引かれた額面の金額なので、年収が130万円以下であれば問題ありません。
\30秒で上限金額を計算できる!/
「支払い金額」と「家族構成」を入力するだけ!
ふるさと納税の源泉徴収票に関するよくある質問
ここではふるさと納税における源泉徴収票に関するよくある質問を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
寄附限度額の確認はいつの年収で計算すればいい?
ふるさと納税における寄附限度額の確認は、寄附をする当年の年収で計算しましょう。2024年に寄附を行う場合は、2024年1月1日~12月31日までの年収があてはまります。ふるさと納税を行う前に、あらかじめ寄附上限額を調べておきましょう。
実際の控除額はどこを見て確認すればいい?
実際の控除額は5月・6月頃に居住自治体から送られてくる、住民税決定通知書の「寄附金控除」もしくは「税額控除額」の欄を確認しましょう。控除対象は、ふるさと納税を行った翌年度(6月~翌年5月の期間)納付の住民税です。
給与所得と課税対象額の違いは?
「給与所得」は年間の給与の合計収入から「給与所得控除」を差し引いた金額をさし、「課税所得」は所得から保険料・所得控除の「所得から差し引かれる金額」を差し引いた金額をさします。
源泉徴収票をもらってからふるさと納税をするのは遅い?
12月に源泉徴収票をもらってふるさと納税を行うと、自治体によって来年分としてカウントされます。限度額が年内分としてカウントされるか不安な方、もしくはカウントされないようであれば、各自治体に問い合わせてみましょう。
まとめ
今回は、ふるさと納税を利用する際の源泉徴収票の見方や再発行の対処法を解説しました。何気なく毎年受け取る源泉徴収票の大切さや、内容を詳しく理解できましたね。ご自身の年収を源泉徴収票でしっかりと確認して、ふるさと納税をたくさん楽しんでください。
ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2024年11月18日)やレビューをもとに作成しております。