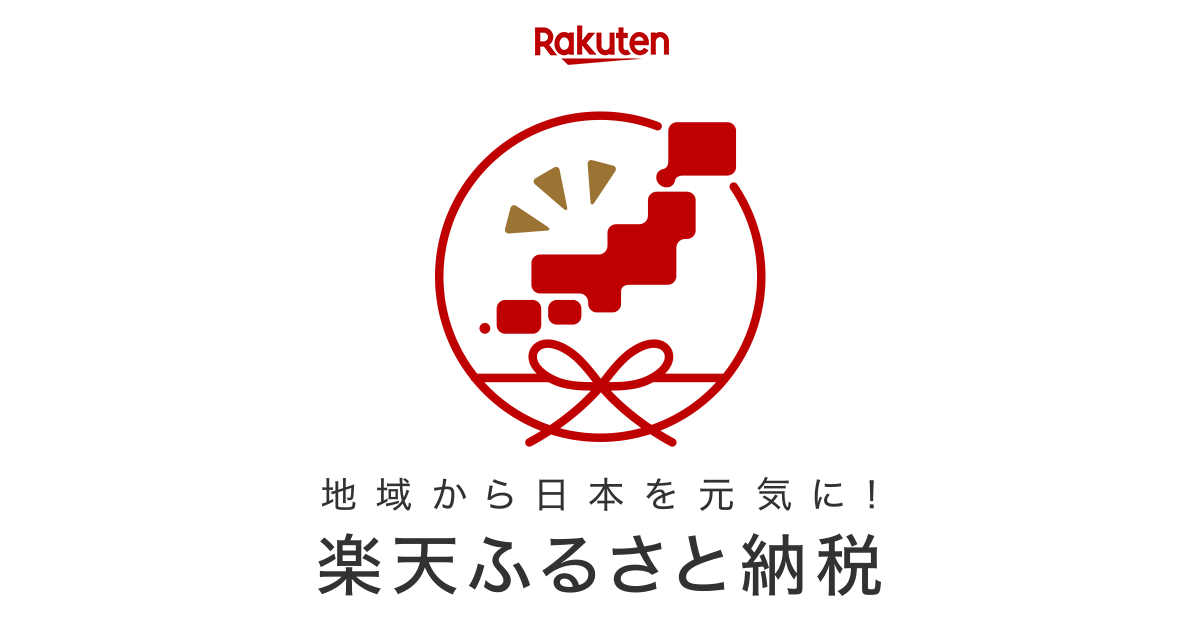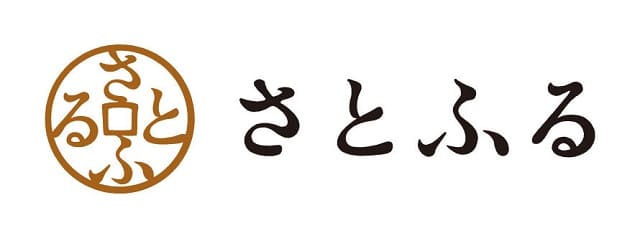ふるさと納税のメリット5つとデメリット6つを解説!仕組みを知ってお得に寄附しよう
2022/04/22 更新

出典: pixabay.com
好みの自治体に寄附を行うと、返礼品が受け取れるお得なふるさと納税。しかし、メリットだけでなくデメリットもあるのを知っているでしょうか?今回はふるさと納税におけるメリット・デメリットを分かりやすく解説します。住宅ローンがある場合や、自営業の方向けの注意点もまとめました。
・当サービスに掲載された情報は、編集部のリサーチ情報を掲載しております。記載の内容について(タイトル、商品概要、価格、スペック等)不備がある場合がございます。詳細については、各EC/サービスサイトでご確認の上ご購入くださいますようお願い申し上げます。 なお、当ウェブページの情報を利用することによって発生したいかなる障害や損害についても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご理解いただけますようお願い申し上げます。
・商品PRを目的とした記事です。gooふるさと納税は、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。 当サービスの記事を経由してふるさと納税をすると、売上の一部がgooふるさと納税に還元されます。
目次
また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
ふるさと納税のメリットとデメリット!仕組みと注意点をチェック
ふるさと納税は好みの自治体に寄附をすると、お礼として返礼品が貰えるお得な制度です。ふるさと納税は寄附をする側がお得になるのはもちろん、税金を地方自治体にも行き届かせる目的があり、自治体側にもメリットがあります。
しかし、メリットがたくさんあるように思えるふるさと納税ですが、デメリットや気を付けた方がよい点がないか気になった経験はありませんか?特に自営業・専業主婦・学生・年金受給者の方は、ふるさと納税をする際にデメリットがないか気になりますよね。
そこで今回は、ふるさと納税のメリット・デメリットを詳しく紹介します。住宅ローンを支払っている方が気を付けるポイントや、保育園などに支払う保育料が安くなるかどうかも分かりやすくまとめました。寄附を迷われている方は、ぜひ参考にしてみてください。
ふるさと納税の仕組みをわかりやすく解説
ふるさと納税のメリットやデメリットについて解説する前に、まずは詳しい仕組みを見ていきましょう。申請方法ごとの控除対象もまとめたので、チェックしてみてください。
税金の控除が受けられる制度〈税制のメリットを受けられる仕組み〉
ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄附を行うと税金が控除される制度です。税制のメリットを受けられる仕組みとしても知られています。税制とは税金のかけ方などに関する制度です。ふるさと納税では税金が控除されるため、税制のメリットが受けられます。
ふるさと納税では寄附をした分だけ税金が控除される仕組みなので、所得税や住民税を支払っている方はぜひ利用しましょう。控除の申請も難しくはないので、まだ寄附をした経験のない方もこの機会にチャレンジしてみてください。
好きな自治体に寄附をして返礼品を受け取る
ふるさと納税の簡単な流れとしてはポータルサイトなどを通して好みの自治体に寄附を行い、お礼として返礼品を受け取ります。返礼品は自治体によってさまざまなものが用意されているため、サイト内をチェックしながら好みのものを選んで申し込みましょう。
返礼品は基本的に自宅に送られてきます。発送までに時間のかかる返礼品などもあるため、早めに受け取りたい場合には発送時期もあわせて確認してみてください。また、中には旅行券やアクティビティの体験ができる面白い返礼品もあります。
税金の控除を受ける
ふるさと納税は寄附をして返礼品を受け取るだけでは控除が受けられないため、必ずワンストップ特例や確定申告などで申請をする必要があります。
ワンストップ特例制度なら住民税の控除
ワンストップ特例制度を利用して申請をする場合には、寄附を行った翌年の住民税が控除されます。寄附をした金額から自己負担金の2,000円を引いた金額が、翌年の住民税から控除されるため非常にお得です。ただし、控除額には上限があるので気を付けましょう。
また、ワンストップ特例制度を利用する際は各自治体から送られてくる書類に記入をし、返送する必要があります。申請期限は寄附の翌年1月10日までなので、漏れのないように申請してください。1月10日必着なので、余裕を持って申請するのがおすすめです。
確定申告なら所得税・住民税の控除
寄附をした翌年に確定申告をする場合には、所得税と住民税が控除されます。ワンストップ特例制度は住民税のみなので確定申告の方がお得に感じてしまいますが、実際に控除される金額の合計はどちらも同じです。
確定申告の申請期間は、寄附をした翌年の2月16日~3月15日までとなります。書類に記入をして郵送やe-taxを使ったオンライン申請も可能です。申請時期は会場が非常に混み合うため、スマホやPCを持っている方は自宅で申請できるe-taxを利用してみてください。
ふるさと納税のメリット5つ
ふるさと納税のメリットはポイントがつく場合が多い・好きな自治体を応援できるなどが挙げられます。以下で詳しく解説するので、参考にしてみてください。
ポイントがつく場合が多い
ふるさと納税を行うサイトによっては、独自のポイントが還元される場合があります。例えば楽天ふるさと納税なら、寄附額に応じた楽天ポイントが還元されるのでお得です。さらに、クレジットカードで寄附金を支払えば、カード会社のポイントも貰えます。
ポイントを活用するとよりお得にふるさと納税ができるので、サイトを利用する際はポイント還元の有無もチェックしてみてください。また、支払いをする際に使うクレジットカードによってもポイントの還元率が異なるので、併せて確認しておきましょう。
好きな自治体を応援できる
ふるさと納税では好きな自治体に寄附をし、応援ができるのも大きなメリットです。寄附をする自治体は好きに選べるので、お気に入りの旅行先や応援をしたいと思う自治体を選んでみましょう。また、寄附先は1つではなく複数の自治体への寄附も可能です。
もともと自分が住んでいた地元や故郷に寄附もできるため、本当に応援したいと思える地域に税金を納められます。ふるさと納税を扱っている自治体はかなり多いので、好きな自治体に寄附できるかどうか確認してみてください。
返礼品がもらえる
自治体への寄附をすると、お礼としてさまざまな返礼品を受け取れるのも大きなメリットです。返礼品は人気のある肉・魚・米などの食品をはじめ、家具や家電など豊富な種類のものが用意されています。返礼品を選ぶ際は、還元率にも注目してみてください。
中には低い寄附額でたくさんの肉や米が貰える返礼品もあります。肉や魚は冷凍で届けてくれるものも多いので、家族の多い方はぜひチェックしてみてください。
寄附金の使い道を指定できる
ふるさと納税で好みの自治体へ納めた寄附金は、さまざまな用途で使われます。指定の用途に使ってほしい場合には、寄附をする際に使い道を選択しましょう。ふるさと納税を行っている自治体では、寄附金の使い道を明確に提示してくれています。
自治体側にもメリットがある
ふるさと納税は寄附をする側だけでなく、自治体側にもメリットがあります。自治体はふるさと納税によって税金を集められるため、地域の復興支援などに役立てられるのが魅力です。例えば災害などが起きた際、ふるさと納税を使えばより多くの復興支援金を集められます。
また、地域の名前を知ってもらい、知名度をアップさせられるのもメリットです。魅力のある返礼品を用意すれば、数多くの方がその自治体に注目してくれます。
ふるさと納税のデメリット6つ
ふるさと納税にはメリットがある一方で、すぐに効果があるわけではないなどのデメリットもあります。以下で詳しいデメリットについて見ていきましょう。
減税・節税になるわけではない
ふるさと納税は減税や節税にはなりません。住民税や所得税などの税金が控除されるため節税や減税になると考える方も多いですが、実際には寄附として各自治体へ先に納税をしている形になります。そのため、納税額が減るわけではないと覚えておきましょう。
すぐに効果があるわけではない
ふるさと納税を行うと住民税や所得税が控除されますが、すぐに効果があるわけではありません。住民税と所得税でタイミングが異なるため、以下で詳しく紹介します。
所得税は確定申告後の還付
確定申告でふるさと納税の申請を行う方は、申請から約1ヶ月程度で所得税が還付されます。確定申告の時期は2月16日から3月15日までと決められているため、遅くても4月中には所得税の還付が受けられるはずです。より早く還付を受けるなら、e-taxを利用しましょう。
住民税は翌年6月以降に反映
ワンストップ特例制度などを利用している方は、ふるさと納税をした翌年6月以降から支払いが始まる住民税に反映されます。納税をした分から自己負担額を引いた金額が住民税から控除されているので、住民税決定通知書が届いたら確認してみましょう。
手続き・申請が必要
ふるさと納税をした場合、控除を受けるためには必ず申請をする必要があります。好きな自治体に寄附を行い、返礼品を受け取った段階では控除されないので気を付けてください。ワンストップ特例を利用する場合には、各自治体に書類を返送しましょう。
確定申告を利用する場合には、ふるさと納税の証明書を保管しておいてください。証明書やワンストップ特例を利用するための申請書類は、ふるさと納税をした自治体から順次送られてきます。
自己負担2,000円が発生する
ふるさと納税では寄附をした分だけ控除が受けられますが、必ず自己負担金が2,000円発生します。寄附をした金額から自己負担金の2,000円を引いた金額が控除されると覚えておきましょう。寄附をした全額控除されるわけではないので、お気を付けください。
控除の対象は本人名義分のみ
寄附をした金額が控除されるのは、ふるさと納税を行った本人のみです。例えば夫婦でふるさと納税をする場合、夫の名義で行ったふるさと納税で控除されるのは夫の住民税や所得税のみとなります。妻が控除を受けるには、自分の名義で別途寄附を行わなければなりません。
また、クレジットカードで支払いをする場合には、基本的に本人名義のカードしか使えません。妻のふるさと納税に夫のカードで支払いをしてしまうと、無効になってしまう可能性があるので気を付けてください。
控除限度額がある
ふるさと納税には「控除限度額」と呼ばれるものがあります。年収や家族構成などによって上限額は異なるので、ふるさと納税を利用する前にチェックしておくのがおすすめです。上限額は各サイトなどのシミュレーションを使えば簡単に算出できます。
控除限度額を超えて寄附をした場合でも、限度額以上の控除はされません。超えてしまった分は全て自己負担となってしまうため、必ずふるさと納税をする前に算出しておきましょう。
得する?損する?他の控除と併用した時の影響や問題点をチェック!
税金の控除にはふるさと納税のほか、住宅ローン減税や医療費控除などがあります。ここでは、それぞれの控除とふるさと納税を併用する際のポイントを見ていきましょう。
住宅ローン減税と併用ならワンストップがおすすめ
税金が控除されるものの中に、住宅ローンを支払っている方を対象とした住宅ローン減税があります。住宅ローン減税と併用する場合は、ワンストップを利用するのがおすすめです。
ワンストップ特例制度なら控除限度額に変動なし
住宅ローン減税を併用する場合、ワンストップ特例制度を使って申請をすればふるさと納税の全額分を住民税から控除できます。そのため、住宅ローン減税が対象の方はワンストップを利用するのがおすすめです。ただし、ワンストップ特例は利用条件があります。
寄附を行う自治体が5つ以下など、さまざまな条件があるので事前に確認しておきましょう。ワンストップ特例は提出する書類も簡単なので、初めてふるさと納税を行う方にもおすすめの申請方法です。
確定申告なら控除限度額が下がる可能性あり
住宅ローン減税とふるさと納税を併用する際、確定申告で申請をすると所得税・住民税が減った分だけ控除できなくなる可能性があります。場合によっては損をしてしまう可能性もあるため、できればワンストップ特例を利用するのがおすすめです。
確定申告をした場合、ふるさと納税の控除は住民税と所得税の両方で受けられます。しかし、所得税に関してはふるさと納税分が控除された上でさらに住宅ローン控除が適用されるため、金額によっては合計の控除額が少なくなってしまうので気を付けてください。
医療費控除と併用なら控除限度額が下がる可能性あり
ふるさと納税と医療費控除を併用する場合、ワンストップ特例は利用できません。ワンストップ特例の利用には「確定申告の必要がない給与所得者」の条件があるため、確定申告で申請をしなければならない医療費控除を受ける場合には条件外となってしまいます。
また、医療費控除を受けるとふるさと納税の控除限度額が下がる可能性があるので気を付けましょう。医療費控除の申請では課税対象の所得額が少なくなるため、その分だけ控除限度額も低くなると覚えておいてください。
保育料は安くなる?
ふるさと納税をした場合でも、保育料は変わりません。保育料に関しては控除前の金額が算定基準となっており、ふるさと納税をして控除を受けても寄附前と同じです。ただし、医療費控除などに関しては保育料に関係があるので、該当する方はチェックしておきましょう。
損を未然に防ごう!ケース別に注意点をチェック
所得税・住民税の納税額がない方は控除を受けられません。そのため、ふるさと納税をしても全額寄附になり損をしてしまいます。ここではケース別の詳しい注意点を見ていきましょう。
自営業・個人事業主
自営業・個人事業主の方は必ず確定申告をする必要があるため、ワンストップ特例制度は利用できません。収入や他の控除を申請するのと一緒に、確定申告でふるさと納税の申請を行いましょう。また、赤字で申告していると控除を受けられないので注意してください。
自営業や個人事業主の方は場合によっては赤字になる時期もありますが、年末には黒字になっている可能性もあります。そのため、年の途中の段階では控除上限額が分かりにくいのもデメリットです。そのため、ふるさと納税をするなら年の後半になってからがおすすめです。
公務員
公務員の場合には、職場にバレてしまう可能性があると覚えておきましょう。ただし、公務員であってもふるさと納税自体はして良いもので、復興支援や地域支援などの目的や理由であれば自治体への寄附を理解してもらえる場合がほとんどです。
ふるさと納税の有無がバレてしまう可能性は低いですが、公務員だと住民税の控除データを管理している担当者などにはバレてしまう場合があります。
年金受給者
年金受給者のふるさと納税では、控除を受けられない場合があります。65歳未満で公的年金などの受給額が105万円以下、65歳以上で公的年金などの受給額が155万円以下の場合は控除を受けられません。年金の受給額によって上限額が変わると覚えておきましょう。
学生・主婦(夫)
学生や主婦(夫)のふるさと納税では、給与所得が103万円以下の場合は所得税がゼロになるので控除を受けられません。ふるさと納税は支払うはずの税金を先に寄附の形で納めるものなので、もともと支払う税金のない方は基本的に対象外となってしまいます。
株の取引をしている
株やFXなどで利益を得ている場合には、確定申告で申請をすると控除上限額がアップする可能性があります。基礎控除額である38万円を超える利益を得ている場合には、確定申告で収入の申請を行ってふるさと納税の控除上限額をアップさせましょう。
まとめ
今回はふるさと納税におけるメリットとデメリット、気を付けるべきポイントについて解説しました。メリットの多いお得なふるさと納税ですが、専業主婦や学生が利用する場合には損をしてしまう可能性もあります。本記事を参考に、よりお得に利用してみてください。
ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2022年04月22日)やレビューをもとに作成しております。