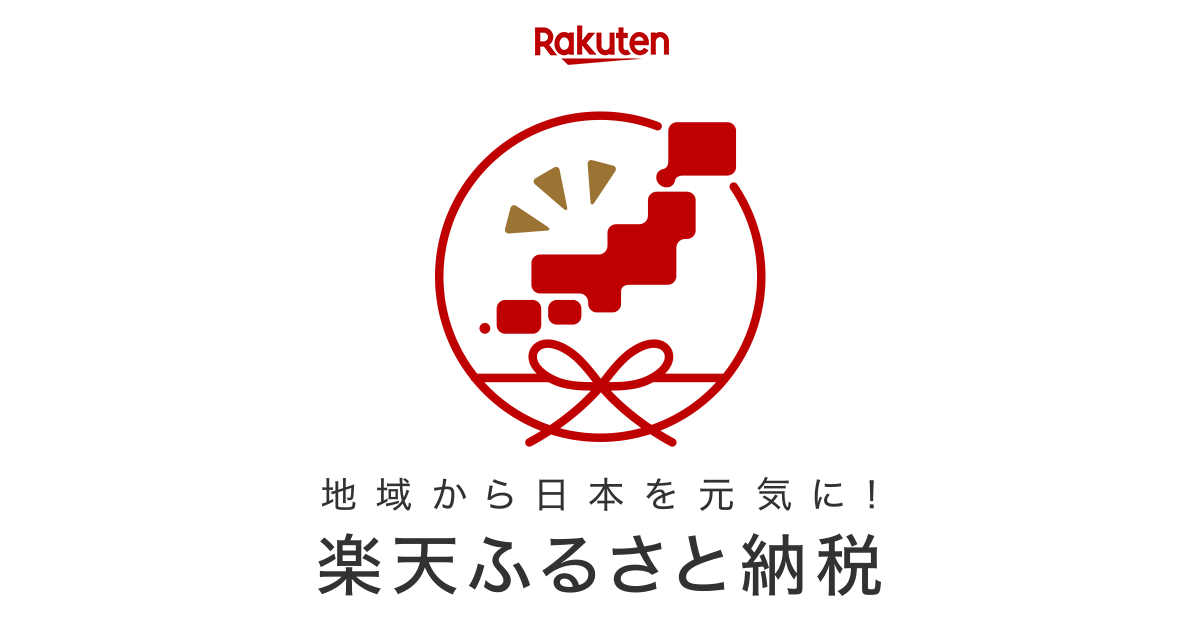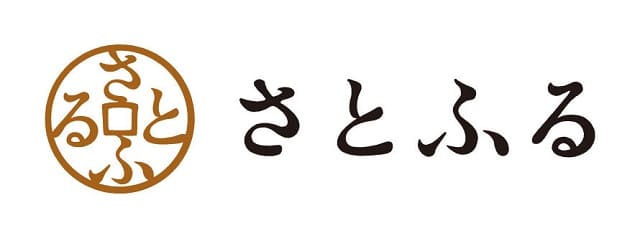専業主婦はふるさと納税で控除を受けられる?旦那の代わりに手続きを行う場合の注意点を解説
2024/10/28 更新

出典: pixabay.com
ふるさと納税は寄附する代わりに税金の控除を受けつつ返礼品がもらえるお得な制度。しかし、収入のない専業主婦・主夫の場合は利用できるのかどうか気になりませんか?
この記事では扶養されている専業主婦の方が「夫名義」「旦那の代わりに」ふるさと納税が利用できるのかを解説し、おすすめの返礼品を紹介するので是非参考にしてください。
・当サービスに掲載された情報は、編集部のリサーチ情報を掲載しております。記載の内容について(タイトル、商品概要、価格、スペック等)不備がある場合がございます。詳細については、各EC/サービスサイトでご確認の上ご購入くださいますようお願い申し上げます。 なお、当ウェブページの情報を利用することによって発生したいかなる障害や損害についても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご理解いただけますようお願い申し上げます。
・商品PRを目的とした記事です。gooふるさと納税は、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。 当サービスの記事を経由してふるさと納税をすると、売上の一部がgooふるさと納税に還元されます。
目次
また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
専業主婦は控除を受けられない!旦那の代わりに手続きは可能!
結論、専業主婦&専業主夫の方は、ご自分名義でのふるさと納税はするだけ損をします。
専業主婦・主夫の方はもともと住民税・所得税がかからず、ふるさと納税をしても控除されるものがありません。そのため寄附をしても全額自己負担で損をします。
しかし、収入のある配偶者の代わりでのふるさと納税はできます。その場合、配偶者本人からの許可に加えて、以下の組み合わせでの寄附が必要です。
| 配偶者の代わりにふるさと納税をする場合 |
|
配偶者名義でのふるさと納税サイトの登録 + 配偶者名義のクレジットカード |
配偶者の年収がわかっていれば、おおよそいくら分の寄附が可能かはすぐにわかります。まずはシミュレーションでどのような返礼品が受け取れそうか確認しましょう。
\今年の年収と家族構成を入力するだけ/
2023年の締め切りは12月31日まで!
専業主婦(主婦)とふるさと納税のポイント
・収入がない自分名義では全額損になる
・配偶者の代わりに行う場合は、「配偶者名義+配偶者名義のクレジットカード」の組み合わせ
・配偶者の年収を把握しておく必要がある
そもそもふるさと納税とは?専業主婦にも関係ある?
ふるさと納税は任意の自治体への寄附を行い、所得税・住民税から控除(還付)を受けるとお得になる仕組みです。そのため、税を自身で納めていない専業主婦・主夫の方は控除(還付)も受けられません。
しかし、配偶者に収入がある方は、配偶者名義ならふるさと納税を利用できます。そこで今回は専業主婦・主夫の方がお得に賢くふるさと納税を行う方法や、配偶者が会社員の場合の控除上限額計算の方法などを紹介します。
また、パートやアルバイトで収入を得ている主婦・主夫の方向けの計算方法や、押さえておきたいポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
▼食材から日用品・家電まで!返礼品をチェックしてみる
専業主婦・主夫が「自分の名義で」ふるさと納税をすると自己負担になる
ふるさと納税は地方自治体への「寄附」ですので、基本的には働いているかどうかに関係なく行えます。
ただし専業主婦・主夫の方は、自分の名義でふるさと納税をすると全額自己負担となります。純粋な寄附目的の場合など、一部のケースを除けばデメリットが大きくなります。
ふるさと納税の最大の魅力は返礼品ですが、返礼品を受け取るためにはまず一度寄附を行います。そして1年間の寄附金額合計のうち、2,000円を除いた分が所得税・住民税から控除(還付)されてお得になる仕組みです。
(例)寄附額30,000円の返礼品を注文した場合
| 30,000円を自治体に寄附 | ||
| ↓ | ||
| 返礼品が届く | ||
| ↓ 控除を受けられる方:実質の自己負担は2,000円のみ! |
||
| 翌年納める所得税 から控除(還付) |
翌年納める住民税から控除 | 2,000円は 控除されない |
|
控除されない方:30,000円は自己負担 |
||
▼ふるさと納税の仕組みを動画でわかりやすく解説!
一定の収入があるパート主婦はふるさと納税が可能
専業主婦ではなくパートで働いている場合、ふるさと納税ができます。ただし、ふるさと納税で得になるかは年収次第です。
返礼品の還元率は寄附額に対して最大30%と定められているため、「自己負担2,000円以上の返礼品」がもらえないなら損をします。
|
パート主婦がふるさと納税をする場合 |
|
|
年収103万以下 |
元々住民税・所得税ともにかからないため控除されず損をする。 |
| 年収130〜200万円 | 自己負担2,000円と同等か少し多い程度の価値の返礼品が受け取れる。手間のわりに金銭的なメリットは薄い。 |
| 年収201万円以上 | 夫婦それそれ別でふるさと納税をするべき。自己負担2,000円以上の価値のある返礼品が受け取れる。 |
明確にメリットがあるのは年収201万円以上です。
パートで「年収150万円の壁」で働いている場合、ふるさと納税自体はできますが、自己負担2,000円以上の価値のある返礼品は受け取れません。
パートでも扶養を外れて働いている場合は、ふるさと納税をするメリットがあります。
専業主婦・主夫でも「配偶者の名義」ならふるさと納税をお得に活用できる!
ふるさと納税は専業主婦の方は夫の名義で、専業主夫の方は妻の名義で行うのがおすすめです。夫・妻が会社員などで所得がある場合、その所得に応じた納税が行われているはずです。その配偶者名義でふるさと納税を適切に行えば、配偶者の納税分から控除(還付)が行われます。
なお、控除を受けられる額には上限があり、上限額は年収や家族構成などに応じて決められています。各ふるさと納税サイトの多くは控除上限額のシミュレーターを設けていますので、寄附を行う前に上限額の目安を知っておきましょう。
▼今年の年収と家族構成を入力するだけで上限額がわかる
控除限度額の目安|家族構成でどう変わる?
ここでは、専業主夫の方で夫が働いている場合を想定して説明を進めていきます。ふるさと納税の控除上限額をおおまかに算出するのに必要なのは、寄附を行うその年の所得と家族構成です。
ただし厳密には、他の控除を受けているかどうかも関わってきます。住宅ローン控除や医療費控除などを含めた、詳細なシミュレーションを行いたい方は楽天ふるさと納税の「詳細版シミュレーター」を利用したり、ご自身で計算を行いましょう。
▼年収と家族構成で見る限度額の早見表はこちら
▼より詳細な上限額が知りたい方はこちら
子供がいない夫婦のみの場合
夫婦のみで子供がいない場合、夫の給与収入に応じて以下のように限度額が決まります。住宅ローン控除や医療費控除がある場合には、限度額が異なる可能性もあるので目安としてチェックしてみてください。
| 夫の給与収入 | 寄附限度額 |
| 300万円 | 19,000円 |
| 350万円 | 26,000円 |
| 400万円 | 33,000円 |
| 450万円 | 41,000円 |
| 500万円 | 49,000円 |
| 550万円 | 60,000円 |
| 600万円 | 69,000円 |
| 650万円 | 77,000円 |
| 700万円 | 86,000円 |
年収700万円以降も、収入が増えるほど限度額もアップしていきます。夫婦のみの場合には子供がいる場合よりも限度額が高くなるケースがほとんどです。
子供1人の場合
子供が1人の場合は以下の通りです。なお、子供は高校生と想定して計算しています。
| 夫の給与収入 | 寄附限度額 |
| 300万円 | 11,000円 |
| 350万円 | 18,000円 |
| 400万円 | 25,000円 |
| 450万円 | 33,000円 |
| 500万円 | 40,000円 |
| 550万円 | 48,000円 |
| 600万円 | 60,000円 |
| 650万円 | 68,000円 |
| 700万円 | 78,000円 |
夫婦のみと比較すると、扶養する家族が多い分だけ限度額が低いです。とはいえ、年収300万円でも11,000円の寄附ができるので、さまざまな返礼品をお得に受け取れます。
子供2人の場合
子供が2人いる家庭の場合は、以下の通りです。なお、子供は高校生と大学生を想定して計算しています。
| 夫の給与収入 | 寄附限度額 |
| 300万円 | 0円 |
| 350万円 | 5,000円 |
| 400万円 | 12,000円 |
| 450万円 | 20,000円 |
| 500万円 | 28,000円 |
| 550万円 | 35,000円 |
| 600万円 | 43,000円 |
| 650万円 | 53,000円 |
| 700万円 | 66,000円 |
子供が2人いる家庭では、子供1人や夫婦のみと比較すると限度額がグッと下がっているのが分かります。扶養する家族が増えると控除額が大きくなり、ふるさと納税における寄附限度額は低くなるのが特徴です。
共働きで扶養控除がない場合
ここまで専業主婦の方向けの限度額を紹介しましたが、最後に共働きの場合の限度額を紹介します。共働きの場合にはお互いに寄附ができるため、それぞれが収入に応じた限度額を計算して寄附するのがおすすめです。
| 給与収入 | 共働き | 共働き+子1人 | 共働き+子2人 |
| 300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 7,000円 |
| 350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 13,000円 |
| 400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 21,000円 |
| 450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 28,000円 |
| 500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 36,000円 |
| 550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 44,000円 |
| 600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 57,000円 |
| 650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 65,000円 |
| 700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 75,000円 |
子供1人は高校生、2人は高校生と大学生の場合を想定した金額です。どの限度額も目安となるので、ご自身の状況に合わせて計算してみてください。
専業主婦・主夫目線で選びたい返礼品はこちら!
専業主婦・主夫がお得にふるさと納税を楽しむなら、普段から使うシーンの多い日用品や食材などの返礼品を選ぶのがおすすめです。食費や雑費が浮けば家計も助かり、余裕もできます。
食費を浮かせるなら米や肉がおすすめ
家族が多い方や食費を浮かせたい方は、たくさんあっても困らない肉や米などの食材を選ぶのがおすすめです。特にお米はコスパの高い返礼品も多くあり、少額の寄附でもたっぷり届けてくれるのでお米好きの家庭なら非常に助かります。
また、肉類は冷凍で届けてくれる返礼品が多いのでストックが可能です。夫婦のみなどで1回に食べる量が少ない場合には、小分けになったタイプを選んでみましょう。
雑費を浮かせるなら日用品がおすすめ
雑費を浮かせたいなら、ティッシュやトイレットペーパーなどの返礼品を選ぶのがおすすめです。日用品関係の返礼品は多くの自治体が取り扱っているだけでなく、少額から用意されていて種類も豊富なので専業主婦の方でも選びやすいです。
特にティッシュやトイレットペーパーはたくさんあっても困らず、自宅にストックしておくと災害時などにも役立ちます。中には毎月届けてくれる定期便などもあって非常に便利です。
贅沢を楽しむなら高級食材をチェックしよう
普段はなかなかできない贅沢を楽しみたい方は、カニや和牛などのちょっと高級な食材を選ぶのがおすすめです。魚介類なら北海道、和牛なら兵庫県や佐賀県などの自治体が多く取り扱っています。少額の寄附でも高級食材が貰えるものもたくさんあってお得です。
以下の記事では和牛の人気おすすめランキングを紹介しています。ふるさと納税で贅沢をしたい方は、ぜひあわせてチェックしてみてください。
そのほか、ふるさと納税では家電・雑貨やキャンプ用品など、幅広いカテゴリの返礼品が各自治体から用意されています。こちらもぜひチェックしてみてください。
専業主婦・主夫がふるさと納税をする際の注意点
専業主婦・主夫の方がふるさと納税をする場合、名義やアカウント名などに気を付ける必要があります。自分名義で寄附をしてしまうと、控除が受けられなくなる可能性が高いためです。
必ず名義を収入のある配偶者にする
専業主婦の方なら夫の名義に、専業主夫の方なら妻の名義にするようにしましょう。所得の無い自分の名義でも寄附はできてしまうため、誤って自分名義で寄附を申し込んでしまうと全額自己負担になってしまいます。
また「寄附」の性質上、商品の購入などと違って一度入金が行われたらキャンセルができない場合がほとんどです。必ず寄附をする前に名義を確認してください。
決済するクレジットカードの名義にも注意
ふるさと納税を行う際には、登録しているクレジットカードの名義もしっかりチェックしておきましょう。寄附を申し込んだ名義と、決済で使われる銀行口座の名義が、ともに控除を受ける方(つまり収入がある方)で一致していないと控除が受けられない可能性があります。
たとえば専業主婦の方が楽天ふるさと納税を利用する場合は、最初から夫の楽天アカウントを使って申し込みをしたほうが確実です。夫が楽天アカウントを取得していない場合は、新しく夫名義のアカウントを作成し、夫名義のクレジットカードを登録しましょう。
楽天の寄附ページの多くには、申し込みの確定後に変更や訂正ができない旨が記載されています。万が一、自分の名義やアカウント申し込みをしてしまった場合には、すぐに寄附先の自治体などに連絡をしてキャンセルをお願いしましょう(必ずキャンセルできるとは限りません)。
控除を受けるには手続きが必要
ふるさと納税は寄附の申し込みだけで完結するものではなく、税金の控除の申請を行う必要があります。申請方法にはワンストップ特例制度と確定申告の2種類があるので、状況に合わせて申請しましょう。
手軽に申請できるのは「ワンストップ特例制度」
夫・妻が職場で年末調整を受けており、医療費控除などを利用しない場合は、確定申告を行っていない方が大半かと思います。その場合はワンストップ特例制度の利用がおすすめです。自治体に必要な書類を返送するだけで手続きが完結し、確定申告が不要になります。
寄附先が多い場合・元から確定申告が必要な場合は「確定申告」
ワンストップ特例制度は、寄附先の自治体が6つ以上ある場合は利用できず、確定申告が必須になります。また医療費控除を使う場合や、配偶者が自営業等で元から確定申告が必須の場合も同様です。他にも、確定申告のほうが簡単に済むケースがあります。
この確定申告は納税をしている側(収入がある配偶者)が行うことになります。元々会社員で確定申告が必要でない方の場合、確定申告の手間が新たに発生するのは負担ですので、事前によくふるさと納税のメリットを伝え、理解を得ておきましょう。
確定申告の期間は寄附をした翌年2月16日から3月15日ですが、もし間に合わなかった場合は5年以内ならさかのぼって申請が可能です。申告が期限内にできなかった場合の詳しい手続きについては国税庁ホームページまたは最寄りの税務署で確認しましょう。
限度額以上の寄附は自己負担が増え損をする可能性
専業主婦・主夫の方に限らず、ふるさと納税には控除が受けられる上限額が設定されています。1年間(1/1~12/31)の合計寄附金額を上限額以内におさめれば、1年分の自己負担は2,000円で済みますが、上限額を超える寄附はふるさと納税としての控除が受けられません。
控除上限額は、控除を受ける方の年収や家族構成などによって決まります。ふるさと納税サイトの多くは上限額のシミュレーターを設けていますので、寄附を始める前に必ず上限額の目安を確かめておきましょう。
パート主婦・主夫はどちらの名義でふるさと納税するのがお得?
所得のない専業主婦の場合には自分の名義でふるさと納税をしても控除の対象になりませんが、パートなどで収入を得ている主婦・主夫なら自分名義でもお得に利用できる可能性があります。
年収103万以下は配偶者名義がおすすめ
パートで働いている方の年収はさまざまですが、年収103万円以下の場合には配偶者の扶養に入っているケースがほとんどと思われますので、ふるさと納税も配偶者名義での寄附がおすすめです。
扶養に入っている方は所得税が非課税で、年収100万円前後の場合の住民税は年間5,000円前後となります。そのため、寄附をしたとしてもほとんど控除が受けられません。そもそも住民税に関しては自治体によって基準などが異なり、パートの収入によってはほとんど発生しない可能性もあります。
年収130万円以上201万以下なら少額寄附が可能
年収130万円以上201万以下のパート主婦・主夫は扶養から外れ、配偶者特別控除を受けているケースがほとんどです。この場合には、自分名義で少額の寄附ができる可能性があります。年収135万円程度のパート主婦なら、数千円の寄附ができる場合が多いです。
ただし、返礼品の内容などによってはお得にならないケースもあります。ふるさと納税がお得に利用できるのは年収200万円程度からが一般的です。もちろん例外もありますが、パート主婦で自分名義の寄附をする場合には限度額や返礼品の内容に気を付けましょう。
年収201万以上は夫婦でそれぞれ寄附
年収が201万円以上あるパート主婦・主夫の場合には共働き扱いとなり、夫婦それぞれが寄附できます。夫婦それぞれの年収に応じた限度額までの寄附ならお得に利用できるので、自分名義での寄附も楽しみましょう。
まとめ
今回は専業主婦の方がふるさと納税をする場合に気を付けたいポイントや、限度額の計算方法などを紹介しました。自分では所得のない専業主婦の場合でも、夫が働いていればお得にふるさと納税を活用できます。ぜひ本記事を参考に、寄附を検討してみてください。
ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2024年10月28日)やレビューをもとに作成しております。