ふるさと納税で副業が会社にバレる?確定申告でバレないか、控除限度額の計算方法もご紹介
2024/10/26 更新

出典: pixabay.com
副業をしている方は、副業の収入がふるさと納税に影響するのか、内緒で副業しているのが会社にバレるのかなど、気になることが多いのではないでしょうか?会社に副業を申告をしているかどうかなどの状況によって、確定申告も必要の有無が変わってくるので注意が必要です。
この記事では、副業収入とふるさと納税の関係、ふるさと納税によって会社などに副業がバレるのかなどを解説します。
・当サービスに掲載された情報は、編集部のリサーチ情報を掲載しております。記載の内容について(タイトル、商品概要、価格、スペック等)不備がある場合がございます。詳細については、各EC/サービスサイトでご確認の上ご購入くださいますようお願い申し上げます。 なお、当ウェブページの情報を利用することによって発生したいかなる障害や損害についても、当社は一切責任を負いかねますので、予めご理解いただけますようお願い申し上げます。
・商品PRを目的とした記事です。gooふるさと納税は、楽天アフィリエイトを始めとした各種アフィリエイトプログラムに参加しています。 当サービスの記事を経由してふるさと納税をすると、売上の一部がgooふるさと納税に還元されます。
目次
また、10/1以降のふるさと納税制度改正に伴うお礼品の寄付金額の変更及び提供の終了があるので詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
副業も控除対象に含まれるが副業がバレる可能性が高くなる
結論、会社に副業を申告している場合、副業収入も控除対象かつ控除限度額が増えます。
ただし、会社に副業を申告していない場合、副業収入の控除分しか寄附できません。また、ふるさと納税をすると会社に副業がバレる可能性が高くなります。
会社にバレてしまう理由はざまざまですが、住民税の金額差・普通徴収から特別徴収への切り替わりでばれてしまうケースが多いです。
副業が会社にバレる理由の詳細などについては、記事の後半で解説しています。
\副業にも対応したシミュレーションはこちら/
副業収入のある人はワンストップ特例制度を利用できない!

ふるさと納税をしたいBさん
副業収入がある場合の手続きは、どのように行えばいいですか?
ワンストップ特例制度は、確定申告せずにふるさと納税での税金の控除が受けられる制度ですので、副業収入を合算し寄附上限額を上げた方は利用できません。
なぜなら、副業収入額が20万円を超えると確定申告の義務が発生し、20万円以下の場合でも年収に合算する際に確定申告を行う必要があるためです。
寄附上限額を上げるために副業収入を合わせて申告した場合、副業収入額が20万円以下でも税金がかかります。
そのため、寄附上限額以上に税金が増えてしまわないよう、課税額と控除額をしっかりと確認したうえでメインの収入に合算するかどうか決めましょう。
副業を会社に隠しているなら限度額は増えない!
副業で控除限度額を増やせると先ほど紹介しましたが、それは「会社に副業を申告している方」のみです。
「会社が副業禁止で隠している」という方は副業をしても限度額は増えません。それどころか、本業のみより少ない金額しか寄附できない場合もあります。
また、ふるさと納税には会社にバレる落とし穴も!解決法も併せて詳しく解説していきます。
※クリックすると見出しにジャンプします。

gooふるさと納税編集部
会社に副業を申告している方は、この見出しは読まなくてOKです!
以下のボタンから次の見出しをチェックしましょう!
副業が会社にバレる理由
ふるさと納税をすると、さまざまな理由から会社に副業がバレてしまう可能性があります。
理由① 住民税の金額差でバレる
会社にバレる要因でありがちなのが住民税金額の違いです。
会社に雇用されている方の多くが、会社が給料から住民税を納税する特別徴収を行なっています。
そこに副業所得分の住民税が上乗せられると、「給与に対して住民税が大きいから、別に収入があるな」と会社側にバレる場合があります。
会社にバレるのを回避するには、副業所得分の住民税を普通徴収(自分で納付)をしなければいけません。

gooふるさと納税編集部
自治体によっては普通徴収を受け付けてない場合もあるので、確認しましょう!
理由② 普通徴収が特別徴収に切り替わってバレる

ふるさと納税をしたいBさん
普通徴収すればバレないから安心だ!
と考えている方要注意です!
副業が会社にバレないよう普通徴収を選択しても、特別徴収に自動的に切り替わってしまう場合もあります。
特別徴収に切り替わる原因は、ふるさと納税の寄附額が副業分で控除される額を超えてしまったためです。
普通徴収分+勤務先の特別徴収分を寄附すると、会社に届く税金の通知書には住民税の総額が記載され、会社に副業がバレてしまいます。

gooふるさと納税編集部
特別徴収への切り替え判断も自治体によっても異なるので、確認しましょう!
副業を隠していると控除限度額が少なくなる理由
先ほど解説した通り、副業が会社にバレないようにふるさと納税するには、副業所得の控除分しか寄附出来ません。
よって、本業の所得から得られるはずの控除がまるまる無駄になってしまいます。
副業が本業の収入を下回っている場合、寄附額は少なくなってしまいます。バレないがために損をしてしまうのは、やるせないですよね。
1番の解決策は隠さない!副業OKの会社も多い
ふるさと納税で損をしたくないなら、隠さず会社に副業申告するのが1番です。
近年副業を許可する会社が増えています。会社の就業規則などを再度確認し、副業を許可している場合は隠さないで申告しましょう。
本業所得に副業所得を加味すればグッと控除額が増えるのに、隠したいがために損をするのはもったいないです。

ふるさと納税をしたいBさん
副業禁止の会社だから絶対バレたくないんです!

gooふるさと納税編集部
であれば、
「副業の住民税額以内の返礼品を選ぶ」
「ふるさと納税を利用しない」
となってしまいます(泣)
副業収入額にあった最適な申請方法を選ぼう!
ふるさと納税を行うすべての方は、確定申告かワンストップ特例制度のいずれかの申請を行います。
どちらが最適な申請方法かは、副業収入の金額で判断できます。自分の該当する方をチェックしましょう。
※クリックすると見出しにジャンプします。
副業収入20万円以上なら確定申告!
副業所得が20万円以上ある場合、ふるさと納税の有無に関係なく確定申告が必須となります。ワンストップ特例制度は利用できません。
申請期間は、ふるさと納税を行った翌年の2月16日~3月15日となります。書類での申請、もしくはe-Taxを使って申請しましょう。

gooふるさと納税編集部
面倒だな〜と思ってしまいますが、何とか確定申告を頑張りましょう!
副業収入20万円以下ならワンストップ特定制度
副業収入が20万円以下は、ワンストップ特例制度を利用しましょう。
「ワンストップ特例制度」とは寄附を行った自治体から送られてくる書類を記入・返送すれば確定申告なしで控除が得られる制度です。
申請期間は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日までです。自治体によっては早めに締め切っているので、寄附する際は必ず確認しておきましょう。
20万円以下で確定申告すると損をする!?

ふるさと納税をしたいBさん
20万円以下は確定申告しなくていいんですか?

gooふるさと納税編集部
はい!住民税の申告は必要ですが、確定申告の義務はありません。
むしろ20万円以下の方が確定申告をすると、支払う税金が増えてしまう場合があります。
副業収入にも所得税などの税金はかかるので、限度額をアップさせる以上に支払う税金が増えてしまいます。
副業収入が20万円以下の場合、確定申告・ワンストップ特例制度を利用する場合の税金金額と控除金額を比較してください。
副業収入20万円以下・21万円以上の比較
\ワンストップと確定申告どちらがいいか/
迷うならこちら
副業収入込みでシミュレーションするなら楽天ふるさと納税
楽天ふるさと納税の詳細シミュレーションでは、より実際の控除限度額に近い金額の算出が可能です。
他サイトでは省かれてしまうケースもある、副業収入の項目をしっかり記入できます。
個人事業主も使用できるよう、基礎情報(給与収入部分)が必須入力になっていないので、副業収入だけの控除額も算出できます。
シミュレーションに反映できる副業の種類
楽天ふるさと納税シミュレーションに反映できるの副業所得は上記が挙げられます。
なお、近年多くの方の副業スタイルになっているもののほとんどは、雑所得に該当します。クラウドソーシング・FX・アフィリエイトなどによる収入が代表的です。
雑所得とは
該当している方が多いであろう「雑所得」をもう少し深ぼってみましょう。
雑所得とは所得の種類のひとつで、以下9種類の所得のどれにもあてはまらない所得を指します。
驚かれる方もいるかもしれませんが年金収入・個人年金も対象です。生命保険会社で加入した個人年金も雑所得の対象になります。
ただし、満期保険金は一時所得の扱いなので雑所得ではありません。

gooふるさと納税編集部
漏れなく申請して控除額をアップしましょう!
(補足)不用品を売ったときの利益は課税されない
生活用に購入した不用品をフリマアプリなどで売って得た利益は課税されません。
ただし、売る目的で仕入れたものを売って得た利益や、貴金属や骨董品など1点30万円以上の高額商品が売れた場合は雑所得の対象になります。
控除限度額を自分で計算する方法

ふるさと納税をしたいBさん
サイトのシミュレーションではなく、自分で限度額を計算したい!
という方向けに詳しい計算方法を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
①所得を合算して計算する
所得の種類によって所得の計算方法が異なるため、以下の計算を参考にしながらまずはご自身の年間所得を算出してみてください。
- 事業所得=総収入金額ー必要経費
- 不動産所得=総収入金額ー必要経費
- 給与所得=収入金額ー給与所得控除額
- 雑所得=総収入金額ー必要経費
給与所得の場合には源泉徴収票などをチェックすれば、給与所得控除額が分かります。
事業所得や不動産所得がある方は必要経費を計算し、収入から引いて所得を算出してください。
クラウドソーシングなどの収入は雑所得となり、同じように経費を差し引いて計算します。
②課税所得金額を計算する
所得の合計が分かったら、次は課税所得金額を計算しましょう。課税所得金額とは、所得から控除を引いた金額を指します。
所得の中で課税対象になるのは控除額を引いたものなので、社会保険控除や配偶者控除の金額を所得から引いて計算してみてください。
③課税取得金額の10%を算出
課税所得金額が計算できたら、次はその10%を算出しましょう。課税所得金額の10%を以下の該当する計算式に当てはめると限度額が計算できます。
- 195万円未満…住民税所得割額×23.559%+2,000円
- 195万円~330万円未満…住民税所得割額×25.066%+2,000円
- 330万円~695万円未満…住民税所得割額×28.744%+2,000円
- 695万円~900万円未満…住民税所得割額×30.068%+2,000円
- 900万円~1,800万円未満…住民税所得割額×35.520%+2,000円
- 1,800万円~4,000万円未満…住民税所得割額×40.683%+2,000円
- 4,000万円以上…住民税所得割額×45.398%+2,000円
自己負担額は一律で2,000円ですが、金額によって計算式が少し異なるのでご自身の収入を当てはめながら計算してみてください。
要チェック!ふるさと納税の人気返礼品5選

gooふるさと納税編集部
「控除限度額がわかった!」という方にぜひチェックして欲しい人気返礼品をまとめました!
ふるさと納税における副業に関するよくある質問
ここではふるさと納税における副業に関するよくある質問を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
ダブルワークもふるさと納税の対象?
給与所得が2つ以上ある場合もふるさと納税は行えるので、ダブルワークでも可能です。また、副業が給与所得と雑所得のどちらでもふるさと納税を行えます。
ただし、2つ以上の給与所得がある場合、自分で確定申告をする必要があります。
「青色申告特別控除」の場合の控除上限額は?
青色申告特別控除・青色事業専従者控除・小規模企業共済掛け金控除など、給与以外の所得収入者のふるさと納税における控除上限額は、寄附上限額シミュレーションを活用して調べましょう。
詳細なシミュレーションが可能なふるさと納税サイトもあります。
会社員が行う赤字副業とは?
赤字副業は主にサラリーマンなどが行う副業で、税金を抑えるためのものです。
例えば給料として年間400万円の収入がある場合、所得税や住民税は比較的高額になってしまいます。そんなときに利用するのが赤字副業で、経費などで売上を赤字にして税金を抑える方法です。
ただし、悪質な赤字副業は脱税とみなされる可能性もあります。実際に大きな経費がかかっていて赤字になっているのであれば問題ありませんが、不用意な出費を経費として計上するのは危険です。申告の際は正しい売上や経費を計上しましょう。
まとめ
今回はふるさと納税と副業の関係性を詳しく紹介しました。お得にも損にもなることが把握できたかと思います。本記事を参考にしながらお得にふるさと納税を楽しんでみてください。
ランキングは楽天・Yahoo!ショッピングなどECサイトのランキング(2024年10月26日)やレビューをもとに作成しております。




































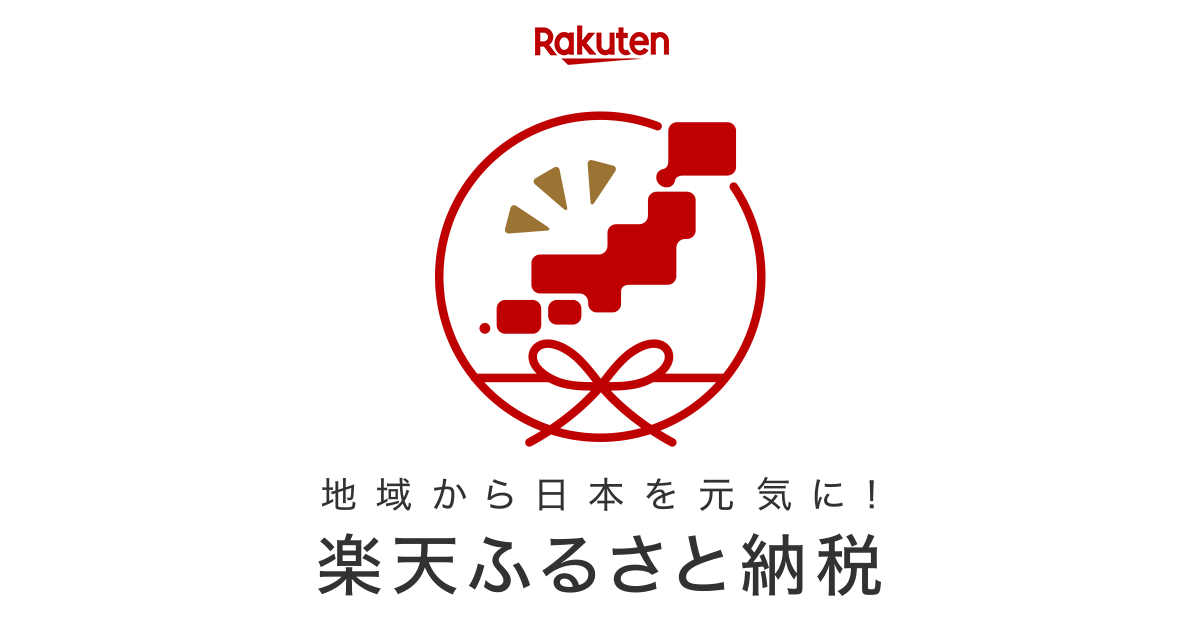
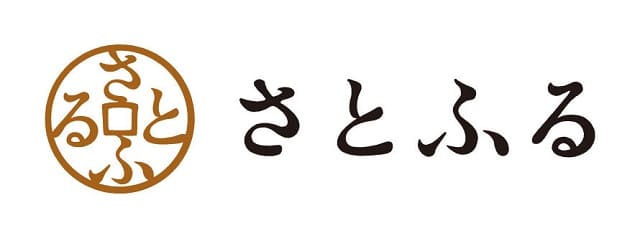



北海道別海町のホタテ返礼品です。訳ありのホタテですが、弾力のある食感と甘みのある味わいが堪らないと人気を集めています。